ミヤマ カヨコ Reviews
妄想CDレビュー「『バ』シリーズ」(ミヤマカヨコ・田嶋真佐雄・二村希一)小島泰子
『バ』シリーズが完結!
昨年、ミヤマカヨコさんと田嶋真佐雄さんのCD『バの5』についてこのブログで発売記念インタビューを決行したが、その後もミヤマさんは続々と「バ」シリーズのCDを制作、ついに『バの∞(無限大)』をもってシリーズは完結した。
そもそも「バ」とはなにか? うーん。
先の「ミヤマカヨコさんインタビュー」から引用しよう。
ミヤマ 意味は、ないのよ。
――え! なんの意味もなく、タイトルをつけたんですか?
ミヤマ なんの意味もないからいいのよ(笑)。貨物列車についてるでしょ?
――ああ、列車に番号がついていますね。そういうことですか。
ミヤマ そういうこと(笑)
なにがそういうことなのか、わかったようなわからないようなだが、「バ」とはそういうことなのだ。
ほかにも、ミヤマさんに、このシリーズについてまだいろいろ訊いてみたいことがあるのだが、インタビューばかりしていてもしかたがないので、ここは私の独断と偏見でレビューを書いてみることにした。妄想でいろいろ間違ったことも書いてしまうかもしれない。それに、音楽に関しては解釈や人の感想なんか読むより、自分のフィーリングで思うままに聴いてみたほうがぜったい得るところ大である、と思っている。私の勝手な解釈や感想なんかは斜め読みしてぜひここに出ているジャケットの写真を見て好きなのを聴いてみてください。
またCDは完結しても、このシリーズのライブ(遊楽園)は都内で続いていくという朗報がある。田嶋さんの演奏は、弦を指ではじいたり弓で弾くことにとどまらず、コントラバスをパーカッションのように使って手品のようにいろいろと面白いことをする。二人のあいだでいろんなハプニングが起きていくのをステージで体験する楽しさも、説明することができない。「ミヤマカヨコさんインタビュー」のページ冒頭で最新ライブ情報を更新しているので、ぜひチェックしてみてください。
さて、どういう順番で紹介しようか。新しいものから古いものへ? 古いものから新しいものへ? あるいは、「バ」シリーズのなかでも「外伝」と銘打たれたスタンダードのアルバムから紹介しようか。誰でも知っている曲が入っているので、親しみやすいかもしれない。だがタイトルの順番から言うと「∞(無限大)」を最後にもってくるのが、よさそうな気がする。やはり、「バ」シリーズ最初の『バの5』から、制作された順に紹介することにしよう。
『バの5』
ミヤマカヨコ(Vocal&Voice)
田嶋真佐雄(Contrabass)
収録曲
1.東京のパレパレさん
2.カリンカ/バの5
3.かえるのうた
4.ウスクダラ
5.みやまかよこでふ
6.桃太郎
7.恋のピンピロリン
8.木曽節
「バ」シリーズ最初のCDだが「5」である。「バ」に意味がないように、「5」にも意味がないということだ。 ジャケットは萬鉄五郎(よろずてつごろう)氏の『日傘の裸婦』の構図を借りて、ミヤマさんご自身が描いている。顔の部分はミヤマカヨコさんなので、自画像とも言える。
インタビューでは、ミヤマさんはこの絵の裸婦はお日様を浴びて自分の使ったところを消毒している昔の娼婦だ、と説明してくれたが、ほんとうだろうか? 萬鉄五郎さんがそれを聞いたらびっくりしてお墓の中でひっくり返っているのではないか。日傘が破れ傘になってるし。
しかしミヤマさんにインタビューで「このCDのテーマは『女』なのね。それもあまり幸せじゃない女。よく考えたらそこに自分が投影されてるわけなんだけどさ」と言われれば、そういうことなのか、と腑に落ちてしまうのである。それは事実であるかどうかはわからないが、ミヤマカヨコさんにとっての真実なのである。
1.東京のパレパレさん (Anfu)
付き合っていた男にふられてオサラバ、アバヨする歌で曲調はマイナーだが、「せいせいしたよ」と言っており、スキャットも「ピロピロリン」と明るく、湿っぽさはまったくない。歌のバックに軽やかで弾むような低音のベースのリズムに、馬頭琴が弓で奏でるような「嘆き声」が挿入され、パーカッション的な効果音なども聴こえてくるが、実は多重録音で、田嶋さんがひとりでコントラバスを駆使した八面六臂の活躍をしているのである。
この曲はミヤマさんの過去のアルバム『スッカラカンノカン』及び『Amazing Kayoko Miyama』に収録されている歌詞のないスキャットだけの「パレパレパン」に歌詞がついたもので、うまく歌がはまった、とミヤマさんはゴキゲンだった。
2.カリンカ/バの5
軽やかな前曲が終わると、いきなり地の底から這いだしてきたような恐ろしい怪獣の叫び声が響き渡る。ギャオォーーウ。いったいなにが始まるのか? おもむろに「カーリンカ、カリンカ…」あの有名なロシア民謡のカリンカの1節が昇降をくりかえし、いろんな方向に引き延ばされたり、圧縮され、照度を変え、ねじられ、しぼられ、変容していく。民謡「カリンカ」は、大きなクマが牧場にやってきて牛に襲いかかろうとするのを娘が必死でとめようとしている歌なので、最初の叫び声や、コントラバスが竜巻のように巻きあげたり、ギーギーと軋んだり、ギューッと搾り上げたりしているのは熊の暴れているようすを表しているのかもしれないがよくわからない。
3.かえるのうた
ミヤマさんのわらべうたアレンジはすごい。エロスとホラーに満ち溢れている。「かえるのうた」も「おまえのすねにスリスリしたい、ジャリジャリ、ズリッズリッ…」というような歌詞で、「ジャリジャリ」にベースの擦過音が呼応している。途中でリズムがスウィングに変化していくところは、田嶋さんとのコンビならでは音楽的な洗練がある。そして最後のミヤマさんのせりふで人間がこわれ、脳みそが縮んでいく恐怖につきおとされる。まさにホラーである。
4.ウスクダラ
ミヤマさんは「アホンダラ」のユニットでこのトルコの伝承歌をチンドン太鼓の伴奏で歌っていたときは原語に忠実だったが(アルバム『スッカラカンノカン』に収録)、今回は日本語で、それも訳詞ではなく、創作の短編小説になっている。恋人だった二人がよく行ったお店に「知らないトルコの歌が流れていたね」とお話のなかで「ウスクダラ」が客体化されているのはおもしろい。エスニックな雰囲気のスキャットも効いている。
5.みやまかよこでふ(Anfu)
この曲は「アホンダラ」のユニットで毎回演奏されていたので、チンドン太鼓で盛り上げるお囃子の印象が強かったが、今回はベースをバックの演奏にした新しい色に塗り替えられている。スキャットの部分はとても自由でのびのびしている。ベースの音が転調をくりかえして低くなっていくのに比例してミヤマさんのスキャットが高まっていくところも面白かった。
6.桃太郎
これも大傑作な大人のわらべうたアレンジ。ミヤマさんの歌詞がすごい。別れ歌になっているが、かわいたユーモアがある。ミヤマさんの歌舞伎の素養が生かされており、歌うように語る(語るように歌う)セリフが歌舞伎役者のようにキマっている。歌舞伎は日本製ラップかもしれない。「そんなに好きじゃないけれど、いらないさっさとあげちゃった」。太鼓チックに始まったり、曲調の変わるところでギコギコの擦過音が使われるなど、ベースがパーカッションのようになったり、そこから切れ目なくコードや旋律を奏でたりする音響の演出も冴えている。
7.恋のピンピロリン(Anfu)
これも内容は恋人に逃げられた悲恋の歌だが、「テンテケテンテテン」の調子良さと頻出する「アレ~」というかけことばでコミカルな雰囲気になっている。歌が終わってから少し間をおいて厳かに響くピアノの音の暗さで、あ、これ悲しい歌だったんだな、と気づかされる。
8.木曽節
インタビューで「なぜ最後にこの曲を選んだのですか?」と訊ねたが、ミヤマさんからは「特に意味はないのね。田嶋さんとやって面白かったから」という答えだった。「なんじゃらほーい?」と訊いたら「なんじゃらほーい?」とコダマがかえってきたようなものである。
ミヤマ外伝 ~スタンダードの巻~
ミヤマカヨコ(Vocal)
二村希一(Piano)
収録曲
1. You'd Be So Nice To Come Home To
2. When I fall In Love
3. My Funny Valentine
4. God Bless The Child
5. The Man I Love
6. Lover, Come Back To Me
7. Tenderly
8. The Nearness Of You
私が魅力的だナ、と感じるジャズ・シンガーを思い浮かべてみると、必ずしも声がキレイだったり声量がある人ではない、ということに気付く。なぜだろう、しゃがれていたり、ため息みたいだったり、儚かったり、よじれていたり、ふてくされていたりするような声が、ジャズミュージシャンの演奏にぴったりはまったとき、すばらしい音楽になる。「人間」というものを、感じさせる声、と言ったらいいのか。ミヤマカヨコさんの声はミヤマカヨコさんそのひとである。例えばビリー・ホリデイの声がビリー・ホリデイそのひとであるように。彼らはジャズという音楽に選ばれた声をもつひとたちである。
二村希一さんのジャズピアノの美しい音色はミヤマさんのヴォーカルにふさわしい衣装となり、ピアノとヴォーカルは一体である。そして対話をする。手をつないで踊る。 音楽は解釈するより感じるものだから、背景なんてどうでもいいと言ったらそれまでだが、時代により音楽は変わる。音楽の作られた時代の背景に注目することで、なにか見えてくるものもあるはずだ。若者がロックしか聴かなかった時代が過ぎてラップが全盛になったいま、ロックのようにストレートでないリズムに関してはラップの親父ともいえるジャズに回帰する傾向もみられる。
このCDに収められた8曲は、ほとんどが20世紀の前半、二つの戦争とそのあいだにはさまれた不安定な時代に作られている。しかしそのすべてが戦争ではなくその対極にある恋愛をうたっている。戦争と核の不安におびえる今の時代も、その頃に少し似ている気がする。変化のなかで安心できるものを求めている。ミヤマさんと二村さんはひとつの旋律からアレンジやアドリブの旅に出ていくが、最後はいつもホームである旋律にもどってくる。そこは愛のある平和な場所である。
1. You'd Be So Nice To Come Home To
第二次世界大戦中の1943年にコール・ポーターが作詞作曲した名曲。戦争に行った兵士の、ああ、うちに帰りたいよー、そこでずっと待ってくれているあなたに会えたら、どんなにうれしいだろう、と妻を恋しく思う気持ちを歌っている。
ヘレン・メリルがこの曲をありあまる感情をこめて歌いあげているのはあまりにも有名だが、ミヤマさんの抑制のある歌い方は、名もない兵士が妻を思って密かにつぶやいているようで、むしろリアルだ。スキャットは戦場を吹く風のようにも、兵士の思い描くホームの暖炉の炭がはじける音にもきこえたりするが、ミヤマさんならではの個性的な味がある。キーはDマイナー。
2. When I fall In Love
朝鮮戦争中の1952年に「零号作戦」という戦争映画に使われた曲。ヴィクター・ヤングが作曲し、エドワード・ヘイマンが詞をつけ、同じ年にドリス・デイが歌ってスタンダードとしてヒットした。こんな落ち着きのない世界では恋は始まる前に終ってしまうけど、私が恋に落ちるときは、心の全てをささげるし、その恋は永遠に続くだろう、と静かな情熱を歌っている。
この曲は、たいがいバラードとしてしんみりと演奏され、歌われることが多いのではないかと思われるが、ここでは明るい曲調がピアノのはずむようなリズムに生かされ、それにさらっと乗ったミヤマさんの歌も軽快で、二人でダンスしているみたいだ。キーはC。
3. My Funny Valentine
日中戦争が勃発した1937年にリチャード・ロジャースが作曲し、ロレンツ・ハートが作詞。「あなたは優しくて誠実だけど、イケメンとはお世辞にもいえないわ、髪の毛もくしゃくしゃだし、口元もなんかヘンテコだし、いつもボンヤリしていて……」とさんざんけなした末、「それでもあたしにとってあなたはただ一人のお気に入りのアートなの。どうかずっとそのままでいて」と歌っている。
そんなコミカルな歌詞なのに、メロディーは切なくて哀愁があり、その旋律の美しさゆえにヴァレンタインという不器用で不細工な男の子も、悪口ばっかりいいながらそのヴァレンタインが好きでたまらない女の子もいとしくなり、冒頭のヴァースからうるうるしてしまう。ミヤマさんの声のしゃがれぐあいと、二村さんのピアノの優しいフレージングの組み合わせも絶妙で、私の大好きな一曲。キーはGマイナー。
4. God Bless The Child
第二次世界大戦が始まった1939年にビリー・ホリデイが歌を作り、アーサー・ハーツォグ・ジュニアが作曲した。聖書のマタイ伝第13章12節「持っている者はさらに与えられて豊かになり、持たない者は持っているものまでも取り上げられてしまう」という聖句が冒頭に出てくる。この歌はビリーのお母さんがレストランを開店するときビリーが多額の出資をしてあげたのにもかかわらず、ビリーのお金がなくなったときお母さんに借りにいったら門前払いされた、という悲しいことがあった後に作られたらしい。
ミヤマさんはビリー・ホリデイの歌をうたうとき、本領を発揮する。「Money…(お金)」とつぶやくビリーの声がミヤマさんの声に重なってきこえる。真似ているわけではないのに、歌のフィーリングと声のかすれたようなはかない感じが不思議にフィットしている。ビリーへのオマージュとして聴くこともできる。キーはAマイナー。
5. The Man I Love
関東大震災の翌年の1924年にガーシュウィン兄弟が作った曲。この歌の「The Man」はまだ会ったこともない恋人。未知の彼といつどんなふうに出会うか、そして二人はどうやって結ばれていくかを具体的に思い描いている。関係ないかもしれないけどこの年、革命によってできた国ソ連を世界が承認し、イタリアでファシズムが台頭し、日本が第二次奉直戦争に介入して英米と対立し、アメリカで排日移民法が成立した。思いがけないことが次々に起こる、不確かな揺れ動く時代に、心の中でだけは思い通りのことが起こっている、そんな祈りのようなものを感じる。
この曲も、ミヤマさんのため息のようなかすれ声が曲調にぴったりだ。リズムの変化も聴きどころで、ワルツから始まって、アップテンポのスウィング、うってかわってしっとりとバラード、そしてまた軽快なワルツに戻り、最後は情熱的なファンクでとどめをさす。リズムが変わるたびに風景も変わっていき、心の中の恋人との関係が進展していくさまを思い描くことができる。キーはG。
6. Lover, Come Back To Me
パリ不戦条約が結ばれた1928年にブロードウェイで上演された「The New Moon」というオペレッタのためにこの歌は作られた。作曲はシグマンド・ロンバーグ、作詞はオスカー・ハマースタイン2世。日本語の題名は「恋人よ、我に帰れ」。このアルバムを聴こうと思う人は誰でも知っていると思うので歌詞の説明は省略。
有名な歌なので、いろんな人が歌っているのを聴いたことがあるが、この歌にこんな美しいヴァースがついていたことに今さらながら気づく。そしてミヤマカヨコさんはコーラスではタイミングをずらすテクニックを駆使してユニークな雰囲気を出している。楽器の人たちがアドリブで枠の中ではセンテンスを自由にできるのと違って、歌の歌詞には言葉数と意味という制約があり、曲を理解して解体しなければ、そう自由に変えることはできないものだ。巧者はその柵をなんなく乗り越えてしまう。だから、みなが知っている歌なのに、とても斬新に聴こえる。最後にぴょんぴょんと転調していってシュワッと終わるのもいい。キーはC。
7. Tenderly
1946年にウォルター・グロスが作曲し、ジャック・ローレンスがそれに歌をつけて発表した。1946年は敗戦国日本の極東国際軍事裁判が開かれた年。日本の植民地だった朝鮮は日本の支配から解放されたかと思うと米国とソ連によって二つに引き裂かれ、一つの国として独立することはできなかった。そんな時代背景だが、曲の内容はやさしいロマンチックな抱擁とキスを歌っている。 この曲にはなにか、傷ついた心を慰めるような軽やかで押しつけがましくない優しさがある。ミヤマさんは声や言葉の響きに細心の注意を払って、この曲の繊細な優しさを届けてくれている。2ndコーラスで、二村さんのピアノと対話するように、交互に歌って(ピアノも歌う)いるのも聴きどころ。キーはAフラット。
8. The Nearness Of You
第二次世界大戦が引き起こされるきっかけとなったミュンヘン会談が行われた1938年にホーギー・カーマイケルが作曲、ネッド・ワシントンが作詞した歌で、文字通り、愛する人がすぐそこにいることのかけがえのなさを歌っている。 戦争の足音が聞こえるような、当時を思わせる今の時代に、ミヤマさんがしんみりとささやくように歌うこの曲は、今一緒にいることの喜びの中にはかなさと哀しみの予感を表現し、それでいて、かすかな希望のような余韻も残している。そしてその余韻は音楽を聴き終わったあともずっと続いている。キーはC
『バの7 ハグレファンキー』
ミヤマカヨコ(Vocal&Voice)
田嶋真佐雄(Contrabass)
収録曲
1.あたし~おお牧場はみどり
2.洲崎パラダイス
3.家路
4.線路
5.国立二中校歌
6.乗車券
7.Begin The Beguine
「バ」シリーズ第2弾のこのCDジャケットは、ミヤマさん自身の歌っている横顔の写真が使われている。鮮やかなオレンジの髪の毛で情熱的に歌うファンキーなオモテ面に対し、同じ写真だがウラ面はネガポジ反転で青い幽霊が槍を吐いているような不穏な絵になっている。歌の表面に出ている明るさと裏に隠されている闇の世界を表現しているのだと思う。
1.あたし~おお牧場はみどり 詞:Anfu
『ハグレファンキー』の主人公らしき、晩年になってからグレた女のモノローグが、ギコギコと木を切るようなベースの擦過音のリズムにのってラップのように語られる。「語り手」はたびたび自分の発言にみずから疑問を呈し「アレ?」というさめたつぶやきが絶妙なタイミングで繰り返しさしはさまれる。
2.洲崎パラダイス
フーヨフニョフニョ~。色々な声が聴こえてくるが、多重録音。ミヤマさんが一人で合唱している。不穏なハーモニー。くねくねした生物がうだるような暑さの中で首をあげて宙にふわふわと揺らいでいる感じ。対照的にブォーンと地の底から響くように繰り返されるベースのマイナーのフレーズが効いている。フニョフニョはタンバリンの単調なリズムに乗ってブォーンを包囲し、官能的に絡みついていく……。吉之淳之介の小説に、けだるげな娼婦たちを湿地帯の植物に喩えて描写した作品があったような気がするが、読んだのがあんまり昔のことでよく覚えていない。「洲崎パラダイス」は東京都の江東区にあった遊郭のこと。
3.家路 詞:ミヤマカヨコ 曲:ドヴォルザーク
ドヴォルザークの「家路」のメロディーに乗せて、虐待された子供が「帰る家がない」と訴える。「間」の強調されたリズムを刻む暗いベース音と、多重録音された弦で弾くコントラバスの演奏もさびしげで、子供のモノローグが途切れてお経が始まると、「ああ、子供は死んでしまったのだ」とわかるが、お経の後にまた同じ子供のモノローグが再開される。「あれ?」と思うが、弦で弾くコントラバスはさきほどの暗くさびしげなのと異なり、中央アジアの弦楽器を連想させるのびやかな音が大草原をわたっていく。それで死んだ子供の魂が風になって語っているのだとわかる。
4.線路
鉄道作業員である「しおからごえ」のミヤマさんと「やさぐれごえ」の田嶋さんが「ヨーイトサー」と声をかけあいながら働いている。そこへまのぬけた汽笛の音が聴こえて汽車がすごい勢いで走り抜けていく。この疾走感をミヤマさんがスキャット(?)で表現しているのは、なんと言っていいかわからないが、迫力とスピード感が凄い。そしてまた単調な声のかけあいにもどっていく。演奏者である田嶋さんの発する声をたくさん聴くことのできるレアな1曲。
5.国立二中校歌 詞:本間一咲 曲:生内義夫
校歌をこんなふうに料理しようという発想がまずあり得ない。規則性のあるリズムで不協和音を刻むベースの演奏が始まると、え?曲がちがうんじゃ?と思って思わずタイトルを確認してしまうが、ミヤマさんはその演奏にのって校歌を歌い始める。この不協和音に正調な校歌をどうやってのせているのかわからないが、のっかっている。しかし校歌は不穏なベースの和音とのざらざらした対決のあいだに沸騰し始め、オヨオヨレロレロ……と勝手に盛り上がってヨーデルに変容し、さらに幽霊の嘆き声になっていく。それに伴いベースのリズムも不規則になり、弾んだり沈んだり、変化していく。いったい校歌はどこに行ってしまうのか。しかしミヤマさんはちゃんと校歌に戻り、最初のように不協和音と調和していく。
6.乗車券
この曲は『はぐれファンキー』な女性の秋田県バージョンのようである。「これからひとりで生きていく、それだけ」といったモノローグ的な歌の間にゲゲゲっという咳払いや、意味のわからない早口の夾雑音や叫び声が絶妙なタイミングで混ざり、思わず笑ってしまう。明るい音階でリズムを刻むベースも歌が崩れるタイミングで変な音をガジャジャっと出していて、実にうまがあっている。
7.Begin The Beguine(詞&曲:Cole Porter)
最後は華麗に「ビギン・ザ・ビギン」を歌いあげるミヤマカヨコさん。ベースがバックで控えめに刻むフレーズはどこかで聴いたことがあるぞ。そうだ、10年前のミヤマさんのアルバム『オビヤビヤ』の「旅のはじめ」に似ている。「旅のはじめ」は3拍子で「ビギン・ザ・ビギン」は8拍子だが、デジャヴュな感じがする。しかし「旅のはじめ」と「ビギン・ザ・ビギン」の関係はよくわからない。また最初に出てきた「はぐれファンキーな女」とこの曲の関係も謎につつまれている。
『バの∞(無限大)』
ミヤマカヨコ(Vocal&Voice)
田嶋真佐雄(Contrabass)
収録曲
1.トンピリピ
2.防災の手引き
3.リリリのフーガ(音楽の贈り物より)
4.隣のドレドレ
5.オンブラ・マイ・フ
6.オンロロバイバイ
7.今死後さ
このCDをもって「バ」シリーズの最後ということなので、終止符、といえるのだろうが、タイトルの∞は終止符が無限大に続いているということなのだろうか? 終わりのない終わりである。シュールな世界である。まるでこの私たちの生きている世界のように。CDのジャケットにいるケモノのような鳥のようなシュールな生きものはミヤマさんかもしれないが、よくわからない。
1.トンピリピ 曲:Andre Popp 詞:Pierre Cour
これはかわいい曲だなあ。あれ、ミヤマさんは何語で歌ってる? フランス語だ! しかし気取りのない自然で可愛らしいフランス語だな。あれ、猫に話しかけてる? 田嶋さんもなんか言ってる。田嶋さんが猫になってる?
2.防災の手引き
テロ、爆発などに対応する防災の手引きが読み上げられているが、すでに災害は発生しているようす。同時進行で気の抜けたサイレンが鳴り、気が変になってしまったレレレのおじさんが、やけに明るい声で「ターッタラッタ・タ・タ・ター」と歌いながらどっかへ駆け抜けていく。ときどき手引きを読み上げる人も発狂する。ギャグな一篇。
3.リリリのフーガ(音楽の贈り物より) 曲:J.S. Bach
ミヤマさんのアカペラに始まって、田嶋さんのコントラバスがバッハの“Das Musikalische Opfer”を奏でる。すばらしい腕前である。そこへもうひとりの田嶋さん(多重録音)のベース音が入ってきてミヤマさんとスキャットの対話をし、コントラバスもその対話に加わり、どこか風変りだが音楽的に調和した心地よい世界だ。
4.隣のドレドレ 詞:ミヤマカヨコ 曲:ミヤマカヨコ
先のバッハの“Das Musikalische Opfer”を同時に聴くと、ミヤマさんとバッハが隣人同士で、どちらがより騒音になっているかを言い争っているように聞こえてドラマチックである。
5.オンブラ・マイ・フ 詞:Minato Nicolo 曲: Georg Friedrich Hendel
不協和音が規則的なリズムで昇降を繰り返すベースとミヤマさんがハミングするヘンデルの格調高いアリアが組み合わせとしてあり得ないシュールな世界に私たちを誘う。
6.オンロロバイバイ 詞:ミヤマカヨコ 曲:ミヤマカヨコ
ミヤマさんのスキャットと田嶋さんのベースの戦闘がクライマックスに達したところで、田嶋さんの低い掛け声が「グォッ」(?)と入るところがかっこいい。この曲は別れを歌っているが、ベースのリズムはのんきに調子がよくて、ずっとリピートでエンドレスにかけてだらだらしたくなるような、怠け心を誘う曲である。
7.今死後さ Traditional
これはミヤマさんの怖いわらべうたアレンジシリーズでも傑作だと思う。日本人がフリージャズの分野でその民族としてのユニークさを普遍に昇華させて世界的になれるとしたら、わらべうたなのではないか。ミヤマさんと田嶋さんには今後もぜひこの路線を貫いてほしいと思う。「死後ってどこよ?」悪夢の中に聴こえてきそうだ。
●プロフィール
ミヤマカヨコ(Vocal)
早稲田大学在学中よりプロ活動。1982年渡米しノーマン・シモンズに師事。1992年~1999年渋谷『ジァン・ジァン』にて毎年コンサート。1996年1stCD『ベスト・リガーズ』発売。同年ツムラ・ジャズヴォーカル奨励賞受賞。2007年スガダイローを共演者に2nd CD『サークル・ステップ』発売。2013年チンドンしげみとユニット結成。2021年contrabassの田嶋真佐雄とのDuoユニット<遊楽園>結成。現在に至る。
田嶋真佐雄(Contrabass)
神奈川県川崎市出身。16歳でコントラバスを手にする。その演奏の幅の広さ、ユーモラスな世界観とガット弦による多彩な音色は特筆すべきである。作曲にも力を入れており、色・景色・匂いを感じさせる作風が特徴である。著書に「ジャズ・ベース・ラインの作り方 」(中央アート出版)。2015年自身のユニットアルバム「倍音の森」をリリース。2019年コントラバスソロアルバム「Self Portrait」をリリース。
二村希一(Piano)
20歳頃から演奏の仕事を始める。鈴木明男クインテット、宮の上貴昭カルテット、遠山晃司トリオ、加藤崇之クインテットほか多数のバンドに参加。自身のクインテットでは「アケタの店」で30年演奏活動を続けている。2002年クインテットのCD「African Marketplace」が発売。2009年トリオアルバム初リーダー作「My Favorite Tunes」、2014年にトリオ第2作「Play for Prayers for K」をリリース。
妄想CDレビュー「『バ』シリーズ」(ミヤマカヨコ・田嶋真佐雄・二村希一) 小島泰子
<鬼才ミヤマ カヨコのバ・シリーズ完結!>
規格外の、超個性派。ミヤマ カヨコはぼくにとって、そう感じずにはいられないシンガー/ヴォイス・パフォーマーだ。なんか、器が違う。何事からも解き放たれ、彼女でしかない確固としたヴォーカル表現を超然と作り上げている様には、毎度頭が下がる。 「変テコ、ですね。ヴォイスと言うと崇高なことをしている方もいますが、そういうのよりはもっと下世話(笑)。ジャズは好きだから離れられない所はあります。こんなちっこくて、こんな声。だから、やっていくなら、これでできる事は何でもやろう、何をやったっていいでしょうという感じですね」 こんなに我が道を進める才人は、一体どんな道を歩んできたのだろう。「OLを3年したあと早稲田大学に入学し、ふとジャズをやってみようかと一時はニューオルリンズジャズクラブに入ったものの、でも合わないしという事から始まりました。そして、歌を習いに行きだし、その後プロになったらと言われて、そのままという感じですね」 態度が軽い。いやフランクで、思い立ったが吉日に好奇心旺盛。1995年にはNYでマーク・ソースキンやマーク・ターナー他らと、完全アコースティックで半分は英語の自作曲を歌う『ベストリガーズ』を録った。その後紆余曲折あり、2007年にはスガダイローとのデュオ作『Circle Step』をリリース。その頃はまだジャズに片足を置いていたものの、現在の方向性のきっかけとなったそう。 そして、以降は奇想天外なストーリーテリング性を抱えた、ジャンル分け不能となるヴォーカル作を次々に発表。一人で作ったものもあれば、チンドンの作り手とやったものもあり。2018年以降はスッカラカンという自己レーベルも持ち、その個性的な活動はより純化もした。 かような彼女は自身のミラクル・ワールドを自在に束ねる”バ“シリーズ(「”バ“には何の意味もない。鉄道車両の車番のようだし、ババアのバでいいかな」)に取り組んでいて、その7作目『バの7 ハグレファンキー』と同8弾『バの∞(8を横にし、無限大とした)』はともにダブル・ベースの田嶋真佐雄とのデュオによる曲を収める。ずしんとした存在感と軽妙なウィットを持つベース音のもと、自在にミヤマのヴォイスと妄想が宙に舞う。「”横濱エアジン“のマスター 梅本さんの勧めでユニットを作ろうとなりました」 オリジナルから出身校である国立二中に校歌や童謡、果ては縁のないバッハの曲まで、自在に素材を扱う。その様はあらゆる雑多さをミヤマ カヨコという個体に集め、そこからドラマチックに噴出させているとも言えようか。その作業はどこか和的な諧謔を抱え(「昭和の人間なので、東宝喜劇の三木のり平とか大好きだし、落語も大好きですね」)、聞く者にあなたはどこまで自由なリスナーになれるのかという問いかけを行う。 ”バ“のシリーズ、8作目にて完結。さあ、次は何が飛び出すか。ともあれ、耳の、音楽観の、ココロの洗濯を!こんなに人間力溢れる癖のある音楽、都市のフォークロア的な内実を持つ表現をぼくは知らない。
(佐藤英輔 Jazz Japan 掲載文)
『バの∞』 (KMAG-0028)
個性派ヴォーカリストのプロジェクトであるバ・シリーズの完結編。依然として危険物取り扱い注意という内容だが、前作の内なる何かとの葛藤を爆発的な危なさで描く感じと比較すると、もっとうちに秘めた感じ。どこか諦観したニヒルなテイストがあり、いうなれば前作は爆薬で、今作は毒物というところだろうか。余計な力は入っていないが全力で放たれる作品群と向き合うには体力も必要だが、聴いた後のカタルシスもある。それでも「防災の手引き」などは思い切った発想で攻めてきていて、聞いているとところどころで、やはり目が飛び出る場面が多いのはこのシリーズの特徴なのだろう。またサウンド的にも田嶋のベースとのデュオで自在は選曲、自在な歌唱をこなし歌も自由。バッハは童謡などと混ざって自身の作詞作曲による楽曲も含まれており、それらは混沌としているが、整理されているようにも感じる。また既存曲には着目点の面白さ、そして微妙に予定調和を崩してくる感じには統一感がある。作品全体にどこかセピア色の黄昏館があり、懐かしい感じもするところは不思議だ。
(鈴木りゅうた Jazz Japan誌掲載文)
『バの7 ハグレファンキー』(KMAG-0027)
個性派ヴォーカリストによる実に狂気に満ちた作品。行儀がよくて薄口の作品が主流を占める時代において、荒くれ者のガサついたカウンター・カルチャーの香りが強烈に充満する。クラシックや唱歌なども収録しているが、それは一部のフレームを借りているに過ぎない内容に思える。基本的に枠組みがない、あるいは破壊していくフリーな世界。ほぼ、田嶋真佐雄のベースとにデュオだが、二人とも音色とレンジが広く情報量が多い。そして何と言ってもミヤマの変態的な発声はジャズからフォーク、ヨーデル、なんでもあり。突如、糸の切れた凧のようにブーンと遠くへ飛んで行ってしまうが、再び帰ってきたりもするため、巨大な渦巻きに飲み込まれたような感覚になり、そうした意味では技巧的。田嶋のベースはしっかりと世界観を受け止めて存在している。形態としてこれをフリー・ジャズと呼ぶことは簡単だが、なんとも不自由な世界を表現し、そこからの脱出を希求する。赤裸々で全てをさらけ出すような歌詞も決して軽くはなく、ガツンと来るはみ出し者のむき出しの叫び。
(鈴木りゅうた Jazz Japan誌掲載文)
CD『ミヤマ外伝~スタンダードの巻~』
個性派にして自称ちょっとヘンテコなシンガーのミヤマ カヨコ。自身のレーベルで自在な歌唱作品を連発している彼女だが、本作はお馴染みのスタンダード曲を、名手・二村希一 の旨味たっぷりのピアノをバックに、そのジャズ歌手としての力量を本格披露する注目作だ。ヘレン・メリルの十八番「You’d Be So Nice To Come Home To」を、メリル風のアンニュイな歌い口も取り込みつつ、自身の唄世界に再構築するなど、全曲どれも彼女ならではの独特な解釈で歌い込み、聴くものをいたく刺激する。
(小西啓一 Jazz Japan 2022 5月号掲載文より)
CD『ミヤマ外伝~スタンダードの巻~』
ベテランシンガーであり、破天荒なヴォイス・パフォーマーとして知られるミヤマ カヨコの自身のレーベルが放つ4作目。メロディのない擬音だけだ全編を埋めてみたり、トンデモ・オリジナルと伝承音楽を交互に並べてみたり、どうやらハグレ型ファンキー曲集も同時発売となる。本作はそんな彼女には珍しく真正面からのスタンダード集。二村の手堅く美しいストライド・ピアノをバックにハミングやスキャットで心に染み入る独特の音世界を作り上げていく。円熟にして、唯一無二な創作行為での手際は、ただただ舌を巻くばかり。 「My Funny Valentine」の歓喜に満ちた官能的パフォーマンス、「God Bless The Child」の圧倒的歌唱力をぜひ聴くべきだ。
(長門竜也 ジャズライフ 2022 4月号掲載文より)
CD『ミヤマ外伝~スタンダードの巻~』
本誌「Vol.66」で紹介した『バ』シリーズからの『バの5』でも素晴らしい歌声を聴かせてくれたジャズ・シンガーのミヤマ カヨコ。今作は『バ』シリーズからの番外編としてジャズ・ピアノの名手、二村希一のピアノをバックにジャズ・ヴォーカルの人気スタンダード・ナンバー8曲を披露している。 ヘレン・メリルの名唱で有名は「You’d Be So Nice To Come Home To」、ビリー・ホリデイ の名唱で有名な「The Man I Love」が特に好きだが、2人の名唱に迫るほど個性的で印象深いヴォーカルを聞かせている。
(The Walker’s 2022 Vol.68 掲載文より)
CD『バの5』
「バの5」発売記念インタビュー(小島泰子さんブログより。掲載の許可を得ています)
シスターフッド:赤線の女たちへの鎮魂歌
ミヤマカヨコさんはジャズ業界で屈指のジャズ・シンガーとして知られてきたが、この十数年、いわゆるスタンダード・ジャズの枠にとらわれない自由な境地を求めて、独自の道をつきすすんでいる。その手法はインプロヴィゼーション、童謡の替え歌、オリジナルソング、江戸歌舞伎、チンドンとのコラボなど、いろいろだが、どれも私小説的に「ミヤマカヨコ」であり、聴く人をその世界にいやおうなく引きずり込む。
今年の秋、スッカラカンレーベルよりアルバム 『バの5』が発売された。これは、ミヤマカヨコさんの最先端が収められたアルバムだ。最初、ここにアルバムのレビューを書こうと思ったが、私の主観的な感想を一方的に書くよりは、ミヤマさんの「声のミュージシャン」としての道のりをうかがい、作品への思いを語っていただくことにより、背景やテーマについてより深く伝えることができるのではないかと思い、インタビューを申し込んだところ、快く受けてくださった。
しかし、インタビューのあとに、自分の生業にかまけて、すぐにアップできなかった。そのため、発売記念インタビューなのに、発売から2ヶ月がたってしまっている。気がつくと、あと1週間もしないうちに新しい年を迎える! 来年の話をすれば、2022年から、ミヤマカヨコさんは2、3ヶ月に1回のペースで毎回1人のミュージシャンと実験的・冒険的なセッションをすることになった。第1回目は西荻窪 「アケタの店」で、1月22日、ドラムの藤井信雄さんと真向から対決する。コード楽器もベースもない、いったいどうなるのか!
ミヤマさんは実験的クリエイティブ路線をめざし、ライブでは長い間スタンダードを歌っていなかった。しかし、この2年ほどのコロナ自粛のあいだ、初めての弾き語りでスタンダードジャズを自宅で録音、日常的にyoutubeにアップされていた。インタビューに挿入してみたのはおもにその動画だ。そのような流れもあり、ミヤマさんのスタンダードジャズのソロライブも都内のライブハウスでしばしば聴くことができるようになったことは、ジャズ・シンガーとしてのミヤマカヨコさんのファンにとって朗報と言えるだろう。
ふだんのミヤマカヨコさんの印象は頭の切れる現実的でシュッとしたシャープな女性だが、舞台の上ではミヤマカヨコさんの声を通してさまざまな存在が出没する。チャキチャキの江戸っ子、童女、さむらいの亡霊、巫女。いったいそれらの存在はどこからくるのかわからない。しかしわからなくていい。謎に満ちた表現者であるミヤマさんの舞台での発光を見届けていきたい。私たちは生命の輝きを受けとることができれば、それでいい。
「私をふったアイツをやっつけるためにジャズ研の扉の前に立ったけど……」
――ミヤマさんの最初のジャズとの出会いについてお話しください。
ミヤマ 私たちの年代では、小さい頃にテレビにエラ(エラ・フィッツジェラルド)とか、サラ(サラ・ボーン)の映像が流れていて、日常的にジャズの歌を聴いていたのよ。アメリカのテレビ番組でも、アンディ・ウィリアムズ・ショーとか、フランク・シナトラのショーなんかも放映していた。そういうのが心のどっかに残っているわけね。でも演奏のほうはあんまり誰のとか、意識して聴いたことがなかった。
高校出て浪人中に、ちょっと付き合ってた男の子がいたの。その子が大学のジャズ研に入ってサックス吹いてたんだけど、「ソニー・ロリンズとコルトレーンが好きなんだ」って言うから、「誰それ?」って訊いたら、「え、知らないの?」ってばかにされるわけよ。そしてすぐその子にふられたのね。もう、すっごいくやしくて「ぜったいコイツをいつか見返してやる」って(笑)。で、初めてジャズのアルバムを買ってみたの。
――それはどんなアルバムでしたか?
ミヤマ 「エラ・イン・ベルリン」だったわ。
――それ、私も大好きです! それで、初恋の人を見返すことができましたか?
ミヤマ その後、すぐには大学生にならず、就職してOLになったの。会社に勤めながら受験勉強して大学に入り、サークルを探す段になって、「そうだ私をふったアイツをやっつけなくちゃいけなかったんだ」って思い出して、ジャズっつうものをやってみようと思ったわけ。そういう不純な動機で始めたわけよ。ぜったいアイツをギャフンと言わせてやるって。それが唯一のモチベーションでさ。で、大学にジャズ研があったんだ、
――早稲田大学のジャズ研ですよね!タモリなんかがいた。超有名ですね。プロもたくさん出ています。
ミヤマ でも、すぐにはドアを叩く勇気が出なくてぐずぐずしたり、まわりをきょろきょろしていたら、ジャズ研の隣に聞いたことのない「ニューオルリンズ・ジャズクラブ」っていうのがあって、そっちはドアが開いてたの。どうぞ入ってください、って言ってるみたいにね。それで、思わず中に入ってなんとなく入部しちゃった。そこはジャズでもデキシーとかをやっていて、そんなの聴いたこともなかったし、ぴんとこなかった。どうしようと思っていたら、先輩も私が迷ってるのに気付いて「デキシーが合わなかったら、こっちのグループに入ってみたら?」と勧めてくれたのが、同じクラブの中でも異端児みたいのが集まってるグループで、初期のマイルス・デイヴィスなんかをやってたわけ。
そのグループにいたら、だんだんジャズが面白くなってきて、ヴォーカルをちゃんとやろうと思い始めて、スクールに入ったの。そしたらスクールではどんどん進級して「あなたプロでやっていったら?」って勧められて。そういう流れね。
「ニューヨークに行って、声出すことについての発想が180度転換した」
――そしてヴォーカリストとして仕事を始められたわけですね。
ミヤマ そう、何もわからないうちに仕事はどんどん入ってくるから、一緒に仕事をしていたミュージシャンにいろいろ教わったり、あれを聴け、これを聴けと言われていろいろ聴いて自分で勉強して……。現場主義ね。仕事をしながら覚えていくという。でも叩き上げなんてえらそうなものでもなく、終わった後の打上げが楽しみでやってるようなところもあったなあ。動機が全部不純(笑)。
そうしているうちに、仲間のミュージシャンがどんどんニューヨークに行きだしたわけ。
私も「行ったほうがいいんじゃない」って言われて。うん、行きたいなーって。でも家庭の事情もあり、長期間行くわけにはいかなかったから、ぎりぎり3か月っていう観光ビザで行ける期間で、思い切って行ったの! そこがひとつの転機っちゃ転機だよね。
――ニューヨークで印象に残っていることはなんですか?
ミヤマ そのころ、好きでよくLPで聴いていたピアニストのケニー・バロンが日本に来たとき、私もケニーの演奏で歌わせてもらえたのね! そのとき、「私、これからニューヨークに行きます」って言ったら、「そのときはライブにおいで」と、ケニーのほかにもニューヨークから来た何人かのミュージシャンに誘われてたから、実際向こうでライブに行くと、客席からステージの上に呼びだされてシットインで歌っていたの。
〈註:シットイン(sit in)とは、ミュージシャンやシンガーが友人や仲間のライブやコンサートに観客として応援に行った際に舞台に呼ばれて共演すること〉
――ニューヨークでは、どんな勉強をされたのですか?
ミヤマ ニューヨークでは、ピアニストのノーマン・シモンズに習いに行ったの。ノーマンは、私の憧れていたシンガー--カーメン・マックレエとか、ベティ・カーター――のバックで演奏してたピアニストなのね。紹介してくれた人がいたから、ああ、いいよ、いいよ、って気軽に引き受けてくれて。もう帰国も近い頃だったから、そんなにたくさんレッスンを受けられたわけじゃないけど、的確なアドバイスをしてくれて。ニューヨークで発声法のレッスンを受けなさいっていうのもそのひとつだったけど、お金もないし、どうしようかな、と思っていたら、一緒にレッスンを受けよう、と誘ってくれる人がいて、ニューヨーク在住のクラシックの専門家に発声を習いに行ったの。そこで今までのやり方をすべて覆されたわけ。それまで5年くらい日本でプロとして歌ってたわけだけど、音楽的な発声なんて習ったことがなかったし。それで、教わったことがすぐにできたわけじゃないけど、声出すことについての発想が180度転換して、日本に帰ってからも、ああでもない、こうでもない、と試行錯誤して、勉強するきっかけになったわけよ。発声について、すごく考えるようになった。
「CDを作るたびに、新しいことを実験しようと決めた」
――それが、いまのミヤマ式発声につながったわけですね?
ミヤマ すぐじゃないよ。すぐにはそこに全然むすびつかない。日本に帰って、しばらくやる気なくなっちゃって、ほとんど歌わなくなったのね。そういう時期がかなり長く続いたの。ちょこちょこ出てはいたけど、自分で納得がいかない時期がずっと続いて、なにしていいかわかんなくて。それで、あるとき、そうだ、自分で曲書こうって思ってさ、ちょうど甥っ子とか姪っ子が生まれたりして、彼らを見ていると自然に発想が浮かんで曲ができたりしてたわけ。そうしてできた曲をライブでやったら、けっこうミュージシャンに評判よくて、作るたびに「いいじゃん!」とか言って励ましてくれたのね。よし、それじゃあ、と。私の尊敬するベティ・カーターが自分で曲書いて歌ってたから、それに触発されたというのもある。今までスタンダード曲しか歌ったことなかったけど、自分の経験を自分の言葉で歌ってみたいと思うようになって……。シンガーソングライターみたいなもんだよね。自分の中から出てきた言葉で曲を作りたいと思った。やってると、なんかそれが楽しくなって、ダメだったのが、だんだんがんばろうっていう気運がまた盛り上がってきて、ちょうどミュージシャンとの良い出会いもあったりして、渋谷のジァン・ジァンで歌うようになったの。その流れのなかで、最初のCDもニューヨークに行ってレコーディングしてみたり――それはオリジナルを形にしたいと思って、行ったのね。
最初にニューヨークに行ったのが1982年、そして、初めてのレコーディングをしにもう1回ニューヨークに行ったのが1995年なの。それもまた大きなチャレンジだった。その後は、初めて自分のバンドも組んで、何年かオリジナルでやってたんだけど、またフェイドアウトしてやらなくなっていったの。2002年にはまたニューヨークへ行ってシーラ・ジョーダンが開催したワークショップに参加したけど、その後も何をしたらいいかわからない時期が続くわけよ。ライブはちょこちょこやるんだけど、そんなにたくさん曲作れるわけじゃないし、何していいかが全然つかめないわけ。そうしているときに、エアジンのマスターが、スガダイローと一緒にやってみないか、って声をかけてくれて。で、ライブをやりつつ、久しぶりに『Circle Step』ってCDを作ったわけ。
この『Circle Step』がいまの活動につながるラインの出発点になったのね。その流れで、こんどのCDもできたわけだし。というのは、その頃ミュージシャンのanfuさんと出会って意気投合して、最初に出したのがこの『Circle Step』で、その後も彼と一緒に作ったCDをどんどん出していったの。ライブもするけれど、それよりCDとして形に残る作品作りをすることにしようと考えを変えたのね。そして、作るたびに、ひとつずつ、実験というか、新しいことをやっていこうって決めたの。クリエイティブなほうに路線が向かっていったわけ。つまり、いわゆるみんなが考えるジャズとはちがうところに向かっていったんだよね。ベースにあるのはジャズなんだけど、いつもやってることと違うことができそうになってきて、やりたいことがだんだん見えてきて、CDをどんどん作っていって……。で、煮詰まっちゃ、チンドンと組んでライブやったりね……。
「これはジャズであるとかないとか、名称なんてどうでもいい」
――チンドンとのコンビはいつもすごく楽しいですね! 私はずっと追っかけていますが......。ところで、いま、ジャズとはちがうところへ、とおっしゃいましたが、私はこの一連のクリエイティブ路線のCDについて、「フリージャズ」というジャンルなのかな、と勝手に考えていましたが、もしかして、「フリージャズ」ともちょっと違うのでしょうか?
ミヤマ そうね。ジャズから始まったけど、これはジャズであるとかないとか、名称なんてどうでもよくなってきたわけ。ただ、ジャズも偉大なミュージシャンがどんどん現れて、いろんな新しいことをして、それをみんな真似して、これがジャズだって昔みんなが思っていたビー・パップみたいなところから、遥かに広がっていってるし、もはや「ジャズとは」って訊かれても、正解はないみたいなところにきてるけどね。
ただ、私の場合は楽器とちがって、「声」だから、さらにもっと自由だなってあるとき気が付いたわけ。声と言葉と、両方使えるじゃん。楽器のような縛りもないし、もっと自由になれる可能性を秘めていると。声についても、かつて発声に悩んでいたせいで、いろいろ研究するようになって――生まれつきいい声の人ってあんまり研究しないんだよ。いい声だねってみんなにほめられて、そのままでいいって言われてたいていなにもしないでそのまま終わっちゃうんだけど、逆に私は生まれつき持ってるものなんて何もないから、研究するじゃん、ああでもない、こうでもないって。ジャズヴォーカルの声だけじゃなくって、いろんな国の、いろんな民族の、いろんな部族の、いろんな声の出し方が、あるわけ。日本のなかでだっていろいろあるでしょ、民謡もそうだし、新内(しんない)、文楽……。人間ひとりひとりだって体の構造が違えば声の出し方だってちがうし、環境がちがえば聴こえ方もちがうわけだし。これはすごいことだな、と思うし。別にジャンル分けする必要もないし、いろんな声だしていいじゃん、と思うようになるわけ。 民謡とか、新内とか、文楽とか、そこにはそれぞれスタイルとか決まりがあって独特な声の出し方がある。でも、ジャンルを決めなければ、決まりなんてないわけじゃん。何やったっていいっていうことになると、いろんな声出せるし、いろんな表現できるし、こんな楽しいことはないと。
――確かにそれは途方もなく楽しそうです!
ミヤマ で、さっき言った声と言葉の、言葉について言うと、そこはある程度制約があって、難しいことも確かにあるんだけど、かつてはスタンダードばっかり歌ってたから頭が英語ばかりに偏って、英語以外で歌うなんて考えられなくなってたのに、そうじゃなくてもいい、となって、別のところに興味が広がっていろいろ自分なりに研究していくと、それぞれの言語が持っている、音感とか語感とか特徴が見えてくるじゃん。そこから、面白いと思ったものはとりあえず全部やってみよう、と。
「ライブではその場で生まれるってことが大事なの」
――面白いと思ったものは全部やってみようと!
ミヤマ できるかどうかはさておき、ためしてみる。日本語だって、自分が今まで思っていた歌い方がすべてじゃない。ああそうか! 歌詞をつけても、こういうふうに歌えばぜんぜん違って聴こえるじゃん、とか、やってみると、いろいろ出てくるんだよ。
――同じ言葉でも、歌い方のちょっとした違いで、意味が変わってくるんですね。
ミヤマ そこんところがいまは面白くてさ。なにやったっていいから。
――ほんとに自由なんですね。ジャズ・シンガーであることにこだわらなければ。
ミヤマ ジャズ・シンガー? そういう顔をするときもあるけど、スタンダード歌ってるときは。ただ、歌とも言えないものも歌ってるわけだから、歌い手? うーん、なんか新しい名前を考えないとな。
とにかく、降ってきたり、湧き出てきたり、いろいろだけど、自分の中にあるものをとりあえず出してみようと、そういう流れになってきてるの。
世界が広がって、しかも細かくもなってきてる。望遠鏡になったり、顕微鏡になったり……。つまり、「神は細部にやどる」という言葉が実感として「そうだな」と思えるようにもなってきたわけ。どっちも現在進行形だけど。 ――それは、いまミヤマさんの作っていらっしゃる自由な「声」の作品のことですね……。
ミヤマ そう、ただ、ライブの場合は、自分一人で歌っているわけじゃなくて、誰かと一緒にやるということがあるわけじゃん、アカペラで全部やるというのもありなんだけど……。昔はピアノとドラムとベースといういわゆるジャズのスタイルでしか音が生まれなかったんだけど、今は、たとえばチンドンとやってみて、そのやりとりのなかでいろいろな新しいものが生まれたり、実験的なベース(田嶋真佐雄氏)とのコンビで、聴こえてくるいろいろな音からヒントをもらったりする。共演者が何かやったことから、インスパイアされて湧き出てくるものがあれば、それをそのまま出してみる、そのときじゃないとできないものだからさ。で、またちがう楽器とやったら違うものが生まれるかもしれない。それは、考えてやるんじゃなくて、その場で生まれるってことが大事なの。CDを作りあげていくのとはまた別の話。
――その場で、というのがライブの命なんですね。
ミヤマ そうそう、だから、そこが、作品としてじっくり作り上げていくCDと違うところなわけ。そうやっていまはCDづくりとライブ、両方でバランスをとっている……というところかな。いつまでこれが続くかわかんないけど。
「感動する音楽って、生命の輝きが伝わってくる」
――波はありますね。
ミヤマ 飽きちゃうと、ぐっと下がって、それを反動にまた新しい波がぐわっと来るっていうのはあるかもね。ずーっと平坦に行くんじゃなくて。
――波があるのは自然なことに思えます。
ミヤマ 音楽ってそういうものじゃん。波というか、律動というか……。ぐわっと来るものがないと。音楽に安らぎとか、癒しとか求める人もいるけど、そういうものがほしいと言われたら、すいませんね、と言うしかない。それはあたしのやることじゃないんじゃないかな、と思ってさ。自分の使命って言ったらおおげさだけど、音楽を何のためにやっているかっていったら、もちろん自分が表現したいからやってるんだけど、受け手がいる限りは、その表現を届けようと思ってやってるわけだから、そこの空間に一緒にいる観客に向かって表現を発して、受け取ってもらって、それが生命のやりとり、みたいなもんじゃん。
こっちの出すものが弱かったら、当然受けてるほうには届いてないかもしれないし、受けてる人の側に拒絶するバリアがあったら届かないってこともあるしさ、それはいつも幸せな関係であるわけではないし、なかなかそういう幸せな関係にはならないかもしれないけど、とりあえずこっちのやることは、「生命(いのち)を発する」ということで……。
――命を削って?
ミヤマ いや、削ってじゃなくて(笑)、「生命(いのち)を輝かせて」ということじゃないかな。その発光が足んないと、ダメだったな、と思うわけよ。たとえば、自分が聴く側にいることもあって、聴いたものに感動することがあると、なにがよかったんだろうって分析するわけ。すると、感動する音楽って、やってる人たちが生命を輝かせて演奏しているのが伝わってくるんだよね。そういうのが好きなんだよ。そういうんじゃないと、満足できないしさ、聴いてて。自分のなかにそういう「はかり」みたいなものがあって、そこに届かないものは退屈だなあ、と思うし、聴いて感動すれば、自分もそういうふうにやりたいと思うし。つまり、生きててこれを聴けてよかった、ありがとう、っていう気持ちになるわけだけど、せめて、自分も、そこまでに至らなくても、姿勢としては、根底にあるものは同じだと思うから、そういうことを大切にしていきたいと。
――ところで、今回のアルバムのタイトル『バの5』には、どんな意味があるのでしょうか?
ミヤマ 意味は、ないのよ。
――え! なんの意味もなく、タイトルをつけたんですか?
ミヤマ なんの意味もないからいいのよ(笑)。貨物列車についてるでしょ?
――ああ、列車に番号がついていますね。そういうことですか。
ミヤマ そういうこと(笑)
「日光浴する娼婦の絵を、顔だけ私にして描いてみた」
――では、ジャケットの絵についておうかがいします。この裸婦像は、髪の毛の色からして、先生の自画像ではないかと勝手に想像していたのですが……。
ミヤマ これは、萬鉄五郎(よろず・てつごろう)さんという洋画家の「日傘の裸婦」という作品のパロディ。顔だけ私にして描いてみたのよ。このCDのテーマは「女」なのね。それもあまり幸せじゃない女。よく考えたらそこに自分が投影されてるわけなんだけどさ。曲つくるときは、シンガーソングライターで、自分にないことはできないから。その「日傘の裸婦」という絵は、昔の娼婦の絵なんだけど、娼婦が日光浴で自分の使った部分を消毒しているような絵なんだよ。
――ご自分をそこに投影するということは……つまり……。
ミヤマ 自分の裸の部分をさらして、思っていることを言ってみました、ってことかな。その右側にあるのは卒塔婆で、赤線のようなところで亡くなったお姉さんたちのためにあってもいいかなあ、なんて思って。その、お姉さんたちが、病気にかかったりして死ぬじゃん、ああいう仕事だから、長生きできなかったりして……。その人たちへの鎮魂歌みたいな意味もあって。
――「南無阿弥陀仏為専唄院金欠空頭姉追善菩提」と書いてあります。これはミヤマさんのことじゃないですか!? ミヤマ そうそう、その卒塔婆の真ん中は自分のことしか書けないから自分のことなんだけど、一応そういう女の代表としての私になってるわけで。
――代表としてミヤマさんがここに座っているけど、実はその後ろに昔ひっそりと娼婦街で亡くなったたくさんの女の人たちの亡霊がいる、ということですかね?
ミヤマ 昔の娼婦だけじゃなくて、今の女性たちもね。女の人今でもみんなたいへんだしさ……たいへんじゃん、男の人より。仕事をしていても、いろいろ。幸せな人ばかりじゃない。
――たしかに。仕事の場のパワハラ、セクハラもそうだし家庭内暴力もあります。考えると、深いですね。
ミヤマ 聴く人にそこまで考えてもらわなくても、いいんだけどね。ま、あえて言わせてもらえば、という話で。
――CDの内容についてですが、1から6までは、今までに発表された作品の中に同じ題名の曲がありますが、びっくりするほど違う曲になっています。例えば「かえるのうた」の以前のアルバム『スッカラカンノカン』バージョンでは2匹のカップルのカエルのかわいらしい対話のようでしたが、今回はとても官能的なモノローグで、「ジャリジャリ」「ズリズリ」(笑)。一瞬笑ってしまったあとに、「あたしの頭、縮んできたよ」なんて来られると、人間がこわれていく怖さを感じました。
ミヤマ それは、もう自分の中からダーッと出てきた歌詞だから、またもう一度作れって言われたらまた全然ちがうものができると思うけど。歌詞を作るときには考え込んだり、練ったりなんかしないで、もう自分の中から出てきたものをそのまま、ダーッと書くわけよ。ほとんど、そういう意味じゃ即興みたいなもんだから。リズムが音符にあうかだけ、歌ってみながら書いていく。
――「ジャリジャリ」「ズリズリ」と……。
ミヤマ みんなそんなこと書かないじゃん。なら私がやりましょ、ということで。
「フラれたけど、ふっきれた東京のパレパレさん」
――「桃太郎」の新しい歌詞も、大笑いしたあとで、「女なら誰でもこういうことあるよなあ」としみじみ思ったりしました。「好きじゃないけどあげちゃった」とか。
ミヤマ そういうことあるでしょ
――あります、あります。
ミヤマ そういうことを遠慮なく書かしてもらいました、て感じで。
――ミヤマさんが「バの5」の中でいちばん好きな曲はどれですか?
ミヤマ どれもそれぞれ好きなんだよ。みんな疲れた女の歌なんだけどさ。……強いて言えば、「東京のパレパレさん」かな……。歌詞がうまいことくっついたから。(アルバム『スッカラカンノカン』及び『Amazing Kayoko Miyama』に収録されている元祖「パレパレパン」は擬音とアドリブだけでこれといった意味のある歌詞がなかった)
――この歌は、ほかの歌に比べてふっきれている感じがしますね。
ミヤマ そうそう、フラれた歌だから、やっぱり内容は暗いんだけどね。
――最後の「木曽節」だけ異色な感じがしますが。
ミヤマ これは、とくに意味はないのね。いつも「遊楽園」(田嶋真佐雄氏とのデュオライブシリーズ)でやっている曲を何か入れようということで。だからこれは田嶋氏とのコンビでできた曲だね。
――ほんとの木曽節というよりパロディみたいなものですね。
ミヤマ これは、私がよくやることだけど、どっかの国の一部族が「西洋音楽を初めて聴いたらこんなふうに聴こえました」というのと同じ流れで、わかんないけど木曽節を聴いてみたら、こんなふうに聴こえました、という「印象の木曽節」であってほんとの木曽節じゃないからね。
――「ウスクダラ」もトルコ語で歌われていた前のバージョン(アルバム『スッカラカンノカン』に収録)と全然違って、物語性があって、面白いと思いました。
ミヤマ 原曲はぜんぜん違う歌詞なんだよ。もとは観光案内みたいな歌なんだけど。これもバッと出てきてがーっと書いた歌で、けっこう気に入ってる。
――私はこういう、ちょっと影がある歌が好きなんですけどね。
ミヤマ 私も影があるのけっこう好きなんだけど、まあ、今回はふっきれた「東京のパレパレさん」ということにしましょう。
(小島泰子さんブログより。)
CD『バの5』
ジャケットに描かれた訳ありげな満身創痍な様子の人物が主人公?、そして…卒塔婆undefined 恐る恐る円盤を回すと、聴こえてくるのはご機嫌で格好いいビートに舞う超絶ヴォーカル その放つ歌詞に思い当たることがあったりなかったりしながら引き込まれていきます …卒塔婆とは五輪塔を簡略化したもの 五輪塔は空・風・火・水・土=宇宙を表すそう 自分から無下に去っていった者へのとむらい、あるいは浮世の憂き節一切合切を宇宙に放り投げたということなのかも⁈ ラストの木曽節は木曽義仲の鎮魂歌、 木曽義仲といえば巴御前、 ヒンドゥー教でいえば戦いの女神ドゥルガーか…
※レビュアーの個人的な妄想です 怒りも恨みも昇華した人間の、異次元な歌宴に招かれた私達聴衆の心も軽やかになること請け合いです。
(Amazonレビュー掲載文より)
CD『バの5』
<ミヤマカヨコワールド全開!>
早稲田大学文学部在学中よりプロ活動を開始。
1982年ケニー・バロンの勧めで渡米し、ノーマン・シモンズに師事。
帰国後、自己のグループを結成しライブ活動を行い、アルバムもコンスタントに発表して来たジャズヴォーカリストのミヤマカヨコ。
通算9枚目の作品で、自身のスッカラカン・レーベルから第三弾リリース作品となる本作。
2021年に結成した「遊楽園-YouLuck\」というデュオユニットの相方、コントラバス奏者の田嶋真佐雄とのデュオ作品で8曲を収録。
ヴォーカル、楽曲、サウンドも凄いが、萬鉄五郎の「日傘の裸婦」にインスパイアされて自身が描いたパステル画のジャケットも凄まじいインパクト。
オリジナリティという表現を超えた一品。
(The Walker‘s vol.66 掲載文より)
CD『大久保日和』
~日本がまだ美しかった頃の歌曲達~
今作は前作とは違い、
和紙に筆と墨で文字を書いていくような、
ピアノと声という編成で、
簡素な中にも様々な色彩が聴こえてきます。
鎖国が解かれたその時から、
未知の音楽と格闘してきた喜びと困難が日本人にはあったかと思うのですが、
どのような境遇にあろうとも、
その根源に戻り追求していくことの不可欠さを、
このアルバムを通して感じました。
なかでも、「波浮の港」は、
発見と創造が展開される瞬間を見たような、
感慨深い演奏です。
情景を描き出す繰り返されるピアノの旋律と、
歴代のどの歌手にもない全く異質な切り口で迫っている歌唱は、ジャズというだけではない、
新しい音楽を聴いた思いがしました。
(Amazonレビューより転載)
CD『大久保日和』
~この世の最後の子守唄~
記号化された言葉に絶望と不信を持つ者にとって、ミヤマカヨコの歌は救いである。
ふつうには、日本語のように平坦な言葉はあまりジャズにふさわしくないと思われる。たいていの人がジャズを日本語で歌うと失敗する。ダサくて古くさい感じになってしまうのだ。しかしミヤマカヨコはその日本語の違和感を逆手にとって、まったく新しい、いなせなローカルジャズの分野を切り拓いている。前代未聞の分野であり、まだ誰も追随するものはいない。しかも、ミヤマカヨコの開拓精神はそこに留まらない。「言葉」にまとわりつく古くさい虚飾に満ちた意味の衣は次の瞬間はぎとられ、純粋な情感のみを留めた「音」にまで解体され、そこから驚くべき素早さでまったく新しい意味不明の言葉がとびだす。その誕生の突然さと思いがけなさは常に爆笑を呼び起こし、そこらにじめじめとただよっていた陰湿な空気は新しく生まれた風に吹き飛ばされ、聴く人は何が起こったのかわけがわからないうちに、自分をとりまく世界が変わったことを知るのである。だから、ミヤマカヨコの「歌」は、ほんとうはその「事件」が起こっている現場で、ライブで聴くのが最高である。
「大久保日和」の収録曲の紹介を見ると、オリジナルの表題作以外、すべてオペラ歌手藤原義江の歌った愛唱歌ということである。曲名はすべて耳になじみのある懐かしい歌だが、藤原義江の名前は知らなかった。YouTubeで検索すると、古いすりきれたレコードが、歪んで波打ちながら回っている映像が浮かびあがり、かすかに針がこすれるノイズとともに、情感豊かな心を打つテノールの声が流れる。
有名な藤原歌劇団を創設した藤原義江はスコットランド人の貿易商と琵琶芸者のあいだに生まれた。子供時代は母について住みかを転々とし、学校も行けず、給仕などをして働いていた。11歳のときに初めて会った父から聞いた言葉は「サヨナラ」だったという。音楽教育を受けたこともなかったが、浅草の歌劇団に入団し、オペラで歌い始める。父が亡くなると遺産でイタリアへ声楽を学びにいく。写真をみると日本人離れした風貌である。日本では異国のひとのように見られただろう。
一方、ミヤマカヨコも「大久保日和」のなかで、「どこの誰だか知らない人ばかり住んでいる街」大久保で自分ミヤマカヨコも異邦人である、と歌っている。ミヤマカヨコと藤原義江に共通する心情がある。それは、生まれながらの異邦人のもつ郷愁。この世界のどこにも存在しない、それだけに常にこがれているふるさとへの郷愁である。そんな切ない郷愁が「大久保日和」にも通底している。
藤原義江とはフィーリングとテーマを共有し、ジャズの形式に則りつつ、懐かしの愛唱歌は変奏と解体を伴う「事件」により新しく生まれ変わり、ミヤマカヨコそのものになった。
9番目のヴェルディの「女心のうた」では、ミヤマカヨコの声の風は最初から最後まで倍速かと思われるほどの早口のスキャットで吹き過ぎる。藤原義江の歌う「風の中の 羽のように いつも変わる女心」を言葉ではなく音で表現するとこうなるであろうという軽やかなめまぐるしさである。最後に昇天していくところは、名曲「ポッペンを吹く女」と響きあう艶かしさに圧倒される。「ポッペンを吹く女」は花魁、「女心」は西洋の奔放なお嬢さんという表現の違いがあるが、本質は同じである。
アルバムの最後の「シューベルトの子守唄」の中では、ミヤマカヨコが一人で子供と大人(父?母?)の役を演じている。ミヤマカヨコの内なる子供の問いかける声が耳から離れなくなる。子守唄を必要としているのは、子供だけではない。命の果てまでたどりついたときにも、夢の中のテーマソングに流れているのが子守唄である。
(Amazonレビューより転載)
CD『スッカラカンノカン』
このCDのなかで、私は2曲目のアカペラの「カエルの歌」が大好き。もともとはみんなが知ってる童謡だが、そこから大発展をとげて、カエルの声だけのデュエットスキャットになっている。デュエットだけれどミヤマカヨコが一人で演じている。1匹は軽いのりの色男ガエルでやや強引に内気なメスガエルに誘いをかけているらしい。メスガエルは最初いやいやながらオスガエルに調子を合わせているが、だんだんその気にさせられ情熱的になっていく。……という物語ではないかと想像して聴いている。
3曲目の名曲「アマポーラ」は、ときどき汽笛の音がさびしくきこえる駅もしくは汽車の中で、「浜松名物甘ポーラ」?の売り子がちんどん太鼓にあわせて、だるそうな声で歌っている。どこかつげ義春の漫画にある旅情を感じる1曲である。アホンダラライブでもよくこの歌はうたわれているが、このCDではよりチンドン色が濃くなっている。
4曲目の「ストレンジャー・イン・パラダイス」は、どことなく不穏で原始的な太鼓のリズムに乗って、多重録音による、違う人格のミヤマカヨコが低音の人から高音の人まで、それぞれ勝手にスキャットしているという、不思議世界。何人いるのか数えられないくらい層が厚く、たくさんの色が混ざっている油絵のよう。いままでも多重録音のアカペラスキャットはよくあったけれど、今回は多彩でありながら調和がとれている点で、一段と洗練されユニークな世界が確立された。
14曲のうち7曲、つまり半分はアカペラだ。 あとの半分はチンドン太鼓と、効果音のサックスのみの参加。 つまりほとんどスッカラカンの歌声だけで、世界の名曲が網羅されている。 それも、さまざまな人格の声で、すべて常人には考えおよばぬアレンジがほどこされている。やはりミヤマカヨコは天才なのだろう。天才であればこそ、スッカラカンでもこんなに豊かな、聴き手の想像を喚起する音楽が成り立つのだ。 アカペラのスキャットはとても魅力的だが、チンドン太鼓の懐の深さにも驚かされる。ラベルのツィガーヌまでチンドンのリズムは飲み込んでしまう! まるでブラックホールみたいだ。
去年のCD、「Amazing Miyama Kayoko」のスウィング、Pale Pale Panも今回はチンドン太鼓バージョンになった。 アルタミラ唱法による「さくら」と「サンタルチア」の、アルタミラ唱法ってなんだろう。ネットには出ていない。おそらくミヤマカヨコが開発したのだろう。もしかしてアルタミラは、旧石器時代の洞窟の名前からとったのかもしれない。西洋の歌唱も日本の歌唱ももとをたどれば原点は同じということを言いたかったのかもしれない。
ところで、最初の曲は、西条秀樹がYMCAの文字を両手でジェスチャーしながら歌っていた元気の良い応援歌だが、ミヤマカヨコは「熱血歌のおねえさん」になって威勢のよい裏声で歌っている。それもアカペラで絶妙な合いの手を入れながらもぴったり拍がはまっている。ヤングマンを知っている世代の人は、これを聴いてショックのあまり椅子から転げ落ちるかもしれない。もしくは「ヤングマン」はかくあるべきという固定観念を持っている人は怒りのあまり飛び上がって天井に頭をぶつけて死んでしまうかもしれない。そうでなくても、突然こみ上げる激しい笑いの発作のために呼吸困難で窒息死するリスクを覚悟で最初の関門を乗り越えてください。固定観念を引き剥がす最初の儀式のあと、軽妙で限りなく自由でなんでもありの楽しい世界がひらけてくるでしょう。
(Amazon レビューより転載)
CD”Amazing Kayoko Miyama/At Last”
<正にアメイジングなヴォイス・パフォーマンス>
都内・横浜を中心にライヴ活動やソロ・パフォーマンス活動を展開している自由自在な独自の世界を作り続けるヴォーカリストのミヤマ カヨコ。
その存在はまだ広く知られていないかもしれないが、まずはこのアルバムを聴いて欲しい。1曲目から正にアメイジングなパフォーマンスと独特の世界観に圧倒されることだろう。ヴォーカリストとしてのエナジーとスピリットとパワーが迸っている。自身のホームページで本作をジャズ・ヴォーカリストの面目躍如たるアルバムと紹介しているが、エリントンの「Heaven」、コール・ポーターの「Night and Day」、ハリー・ウォーレンの「At Last」では、ジャズ・ヴォーカリストの神髄を聴かせている。ぜひライヴでも体感すべき歌技はお見事。
加瀬正之”The Walker’s” Vol.48記載
『Amazing Kayoko Miyama /At Last』CD Review
ジャズが好きで、ヴォイスでそれを表現したくて、だからといってそれが“ジャズ・ヴォーカル”になるわけじゃないことを、ミヤマは生々しく体現させてくれる。
以前の3部作は事象に対しての憑依型だった。不機嫌な女/僧侶らの声明/祭場のノロたち・・・・、また飛び散る火の粉や水を切る舳先にまで声で化けてみせた。
しかし、ここにきてヴォイスは新たな次元に達したらしく、音による絵画創作の現場を突きつけてくることになる。抽象的だった声が重力を得て、ずしりと立体を現わし飛び跳ねだしたのだ。相変わらず超常的発声とその扱いにはド肝を抜かれるし、やはり聴いて納得するしかない声の協働芸術なのである。
長門竜也『ジャズライフ』11月号掲載
『リンラリンラミヤマ』CD Review
2010年3月のブログでも書いたJAZZシンガー・ミヤマカヨコさんの新作 CD「リンラリンラミヤマ」が発売となり、記念ライブが南青山の「MANDAL A」で開催された。
ミヤマさん——カヨちゃんは大学在学中からスタンダード・ジャズを歌いつづけてき た日本でも有数のシンガーである。
それがなにを思ったか、ここへきてトツゼン路線 変更。持ち前のミラクルボイスをひっさげて、なんと「チンドンセット」をバックに 歌いはじめたから、これにはびっくりぎょうてんして、思わず『パスワードまぼろし の水』にでてくる「KAYOKO LOVE」のモデルにさせていただいた。
今回のライブでも、そのエンターテイナーぶりはいかんなく発揮された。たとえば 「やっちゃいけないカリンカ」という歌では、いったい何オクターブあるのかと思う くらいの声域を披露。つい聴き惚れてしまった。
また、エレクトリック・ベースとの 掛け合いでやった「森の石松セッション」は、ただ驚愕・驚嘆・驚聴するのみであっ た。
松原秀行(児童文学作家)
日経新聞2011.12.27「夕刊文化欄・今年の収穫」掲載

おとぎ話の絵本のような特異なボーカル世界を創作し、3枚の作品に完成させた美山夏蓉子の珍しいライブも、今年の印象的なステージだった。
小さな空間にひろげられたこの想像力の翼は何とも魅力的。
(青木和富)
『ポッペンを吹く女』CD Review
『ジャズライフ』3月号掲載歌詞なし。メロディもなし。これほど自己の世界を投影し、独特の風景音楽にしてしまう歌手もあるまい。
そして、アート画も含めひとつの創造物とする美山の感性とエネルギーには心底脱帽させられる。本作はそんな三部作における完結篇となった。
自らこれをピカソの「泣く女」だと言う。
それが日本人なら歌舞伎絵と重なりタイトルとダブってこようが、いきなり不満げに発せられる女のエキゾティックなコーラスで幕を開けて動揺させられる。
やがて経を読む僧侶の集団になり、祭り場のノロの一団となり、火の粉や舳先のきしみにも変貌する。
この世界は日本人ならば一度は体験したことのある、誰もが知る何かなのだ。
(長門竜也)
『ポッペンを吹く女』CD Review
『スウィング・ジャーナル』3月号掲載すげえな。
四方八方に広がる肉声/冒険哲学を、思うままにパックしたアルバムだ。
女をテーマにしたそうな、枠なしのアナーキー盤。
ここでの我が道を行く吹っ切れた指針にふれると、なんと自分はフツーでつまらない人間であるかと、思わずにはいられない。ぶっちゃけ、頻繁に本作を聞けないとは思う。
だが、音楽/歌という人間的行為を真摯に、自由に突き詰めている人(しかも、日本人!)がいるという事を知ることが大切なのだ。
ぼくは、猛烈に感動し、鼓舞された。
(佐藤英輔)
『ポッペンを吹く女』CD Review
『CDジャーナル』3月号掲載美山夏蓉子は、とんでもなく面白い表現者だ。
前作『オビヤビヤ』も驚嘆の世界だったが、この3部作最終作は、さらに想像力のユカイのようなものが彼女の中で暴れ回っているようで、聴くこちら側もただならない世界を前にしているような楽しい緊張が走る。
今回のテーマは女。有名な版画からうまれたタイトルは、江戸の廓の女郎が登場し、まるで演劇のような思いもかけない世界が展開する。いわゆるインプロの即興ではなく、声と楽器のこの即興的一人芝居は、ほかに例がないと思う。音楽は音楽だけじゃないと気づいている。
(青木和冨)
毎日新聞2009.2.9掲載
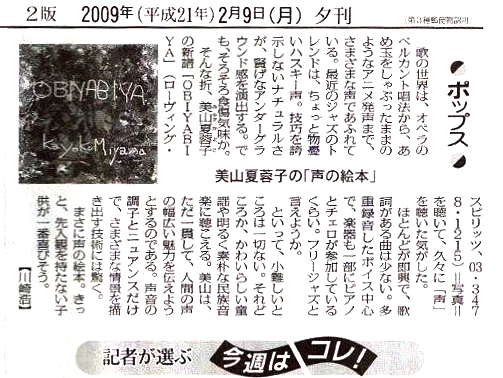
『OBIYABIYA』CD Review
『CDジャーナル』掲載さまざまな意味不明の言語を語る旅人たちが世界を巡るといった、メタファジカルなミュージカル(?)である。
これをほとんど一人でこなす美山夏蓉子が何とも楽しい才能で、この貪欲なというよりも何とも自然な想像力の翼の広げ方がうれしくなる。
物語は想像力を引き出し、その楽しさは新しい技術も生み出すという自然な循環がここにある。
美山はあらゆるジャズ・ヴォーカル、ヴォイスの世界を経てこの世界にたどり着いたようだが、いかにも女性らしい夢を所有したようにも思う。
こんな楽しい声の絵本はない。
(青木和冨)
『OBIYABIYA』CD Review
『ジャズライフ』掲載声は神が人類に与えた最高の楽器だという言葉が頭に浮かんだ。
幾重にも重ねられた時間軸のなかに、さまざまな色を備えた声が詰め込まれ、それぞれ干渉がし合うことで別次元の風景を映し出していく。
歌とヴォイス・パフォーマンスの境界を定めているのはおそらく美山夏蓉子自身の象風景なのだろう。
だからこそ、放たれた声はどれもが無責任な軌道を残して消えていくことなく、ある意志に従って決められた一点に収束していく印象を残す。
音楽というものを分解していくと波長という形態に行き着いて、その原子単位の差異のコントロールが世界観を構築できるまでに至るのだなと物理学的な感動を覚える仕上がりだ。
(富澤えいち)
『Circle Step』CD Review
独自のスタンスで歌の表現に意欲的に取り組む美山夏蓉子さんの2ndアルバム。
若手注目度ナンバーワンのフリー・ジャズ・ピアニスト、スガダイローとのデュオ作品。
シンプルな編成ながらも圧倒的な力強さで迫ってきます。
収録された11曲中、7曲が彼女のオリジナル。
「Black Coffee」「Summertime」といったスタンダード・ナンバーも収められていますが、単に表層部分をなぞっただけのヴォーカルとはまったく異なる独創的な音楽世界を展開しています。
最後に収録した「Michel, My Angel」は、ミシェル・ペトルチアーニに捧げたオリジナル・ナンバーで美しい余韻が残りラストを飾るにふさわしい内容。
歌の本質部分を大事にしながら自己の芸術性を深く追求していく彼女の姿勢からはシンガーとしての強い信念が伝わってきます。
とにかくその圧倒的な表現力と説得力をこのアルバムから感じとって欲しいと思います。
(Amazon Review掲載文より)
『Circle Step』CD Review
『JAZZ TOKYO』掲載美山夏蓉子(ミヤマ・カヨコ)は日本では極めて異色のジャズ・ヴォーカリスト。
即興音楽のヴォイス・パフォーマーともまた違う。
ベティ・カーターが「憧れの存在」で「勝手に『心の師』と仰いでいる」と自身のライナーノートにも書かれていたが、美山のスタイルはまさにそれだ。
11年ぶりの新作は、そういった彼女の志向が強く現れた録音である。共演者は渋さ知らズでも活躍しているスガダイロー。
時にはフリージャズに突入、ピアノとヴォイスのコラボレーションへ。
これは一般的なジャズ・ヴォーカルではあり得ない事態といえる。スガは伴奏者ではなく共演者なのだ。
メロディからより自由な器楽的インプロヴィゼーションへと発展させることの出来るジャズ歌手は日本ではなかなかいない。その実、歌詞つまり唄の世界に深く入り込んでいる。
よく知られた<ブラック・コーヒー>や<ストレート、ノー・チェイサー>もまた独自の解釈で聞かせる。
有名歌手の<サマータイム>をフレーズ毎にコラージュ的に繋げるというユニークな<サマータイム>、一人多重録音<サークル・ステップ>の斬新な発想と表現の豊かさ。アカペラ部分でもしっかりと音程やテンポをキープしているのは、伴奏に頼らずに歌っているからだろう。
冒頭の<ザット・イズ・ユア・タイム>やスリリングなスキャットが印象的なベティ・カーターに捧げた曲<ミズ・ビーシー>がいい。唄はフレーズ、そしてメロディーであり、声もまた楽器なのである。
ゆえに美山の唄は、ジャズの本筋を行っていると言っていい。
地道に活動を続けてきたベテランが放った快作!
(横井一江)
『Circle Step』CD Review
『スイング・ジャーナル』美山夏蓉子とスガダイローのデュオ・アルバムで、ボーカルとピアノのデュオでこれほどの豊かな音楽世界を構築していることに驚いてしまう。
美山はジャズ・シンガー、そしてボイス・パフォーマーであり、自己のボーカル&ボイス表現の可能性を追求しながら、個性的な歌の世界を切り開いている。
曲に独自の解釈を施す歌唱をベースにして、そこから自由自在なインプロビゼーションを展開する。
スキャットを駆使する彼女の即興はアーティスティックであり、まったく自由でどこへでも行けそうだが、音楽として構築することを忘れない。
また、美山のボイスは、時に楽器のようであり、時に鳥のさえずりのようであり、カラフルな色彩感を持っている。まるで肉声を芸術表現の媒介にして魔術師である。
ピアノのスガはそんな美山にふさわしい共演者だ。渋さ知らズや、鈴木勲オマ・サウンドなどで活躍するフリー・ジャズ系のアーティストである。美山とスガは、互いのフリーなジャズ・スピリットを奔放に発揮し、創造的なコラボレーションを進展させながら、音が衝突するようなバトルもみせる。
スタンダードの"Black Coffee""Summertime"、モンクの"Ruby, MyDear""Straight, No Chaser"以外の7曲は美山の作詞作曲。
"Ms. B.C."はベティ・カーター、"Michel, My Angel"はミシェル・ペトルチアーニに捧げた曲。美山の強い思いが込められた歌詞にも注目だ。
"Summertime""Circle Step"はピアノなしで、オーバーダブで、コーラスが加えられており、音楽を構成する手腕も見事である。
(高井信成)


